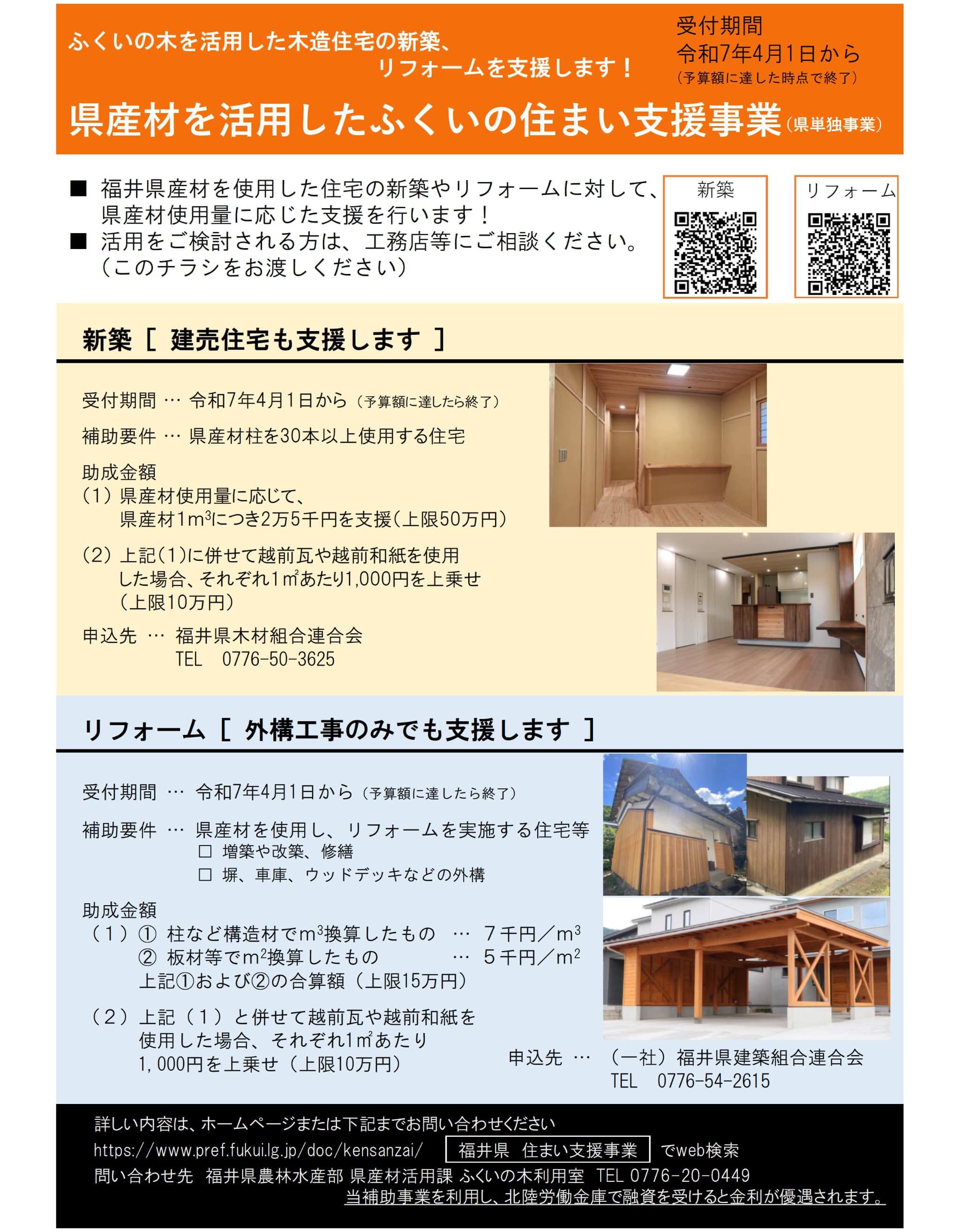ひょんなことから耐震診断と補強プラン作成の研修会を開催することになりましたw 昨年の能登地震以来、福井県下の自治体が展開する耐震診断の補助事業ご希望される方が急増していますが、それらの対応を行う「耐震診断士」さんの数は少なく、自治体では積極的に診断士の募集も行っております。
弊社は平成18年から耐震診断業務を行っていますが、現在に至るまで対応させていただいた数も多く、また、診断だけではなく改修業務も行っており、実績数もあります。ですが、1年間に対応できる数は限界もありますので、診断士さんが増えてくれることはありがたいことです。特に耐震診断や補強プランを作成するだけではなく、改修工事も行うことができる方は貴重な存在で、こういった方は増えてくれることは福井県下の耐震化率をアップさせることにつながります。
ところが、現時点では「福井県木造住宅耐震診断士」としての資格取得のための研修機会はあるものの、具体的な調査方法の研修や、診断報告書の作成といった事務手続き、また、肝心の補強プラン作成にあたってのキーポイントや施工上の肝のようなことを学ぶ機会というのはありません。建築防災協会から発行されている「木造住宅の耐震診断と補強方法」や福井県木造住宅耐震診断士講習会で配布されるセミナー資料だけでは、実務まで見通せるような資料ではありませんので、どうしても初めて診断するという場合にはオロオロになってしまいます。
ところが、今日、お昼時に、たまたま弊社の前を通りかかった大工さんであり診断士さんでもある方が、これもまたたまたま弊社に詰めていた大工さんと顔見知りで、ひょんなことから耐震診断の話しになり、初めて診断することでいろいろわからないことがあるというお話しだったことから、ちょうど午後からは耐震診断の実施調査に大工さんと向かう予定でしたので一緒に同行していただき、診断調査の実務研修となりましたw
この方、大工さんでもあって、勉強され建築士の資格も取得され、耐震改修を手掛けたいということで診断士の登録も行った方ですが、さすがに大工さんだけあって現場感はピカイチです。診断調査の肝というものをお伝えするつもりだったのですが、何を見るべきか、そして何を判断すべきかなど、耐力壁として評価するときの現況状況がどうあるべきかということをお伝えしたところ、すぐにご理解いただけました。
また、今回は実施調査でしたので、実際に床下に潜ったり、天井裏を確認したり、構造状況をつぶさに調べ上げる必要があったのですが、さすがに大工さんです。現場感があって、こちらが構造的にどうあってほしいか?例えば、そこに筋交いがあるという基本調査の結果をしっかりと裏付けるだけの目視等の確認を行ってくれました。
耐震診断で重要なのは、壁が存在していることではなく、その壁が耐力壁として成立しているか?を目視確認できるかであって、基礎があるか、土台があるか、梁があるか、など基本的な確認項目がおさえられないと判断することはできません。


言われてみれば当たり前のことなんですが、やってみるとなかなか大変で、想定していた箇所に柱がない、梁がない、基礎がないというのは古い住宅には往々にしてあることなのです。
こうした調査上の肝というのはやはり実際の現場調査を少しでも経験しない限り、見るべきところを掴むというのは難しいわけで、こうした実際の現場調査に同行していただいてちょっとだけでも研修することで理解を深めることはできるわけです。
明日は、基本調査に出向く現場があるので、ご一緒にどうですか?ということを申し上げたところ、「是非!」ということでしたので、明日も研修を行うことにします♪