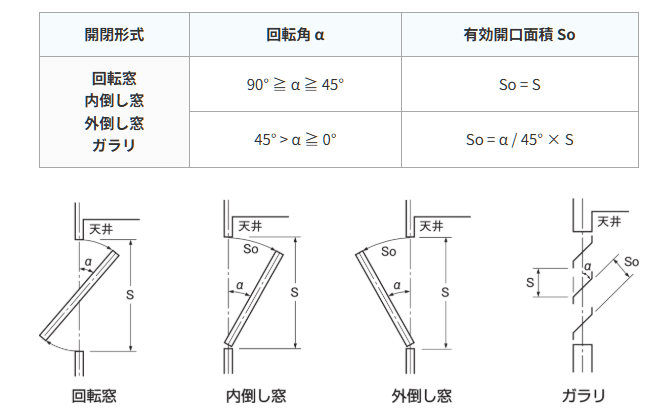8月27日は、ラジ+(TAS)にて第4水曜日にお送りしている弊社ラジオコーナー「福登建設の快適家づくり研究所」の放送でした。

トレタスの入り口のところには、カブトムシとクワガタがうってましたw
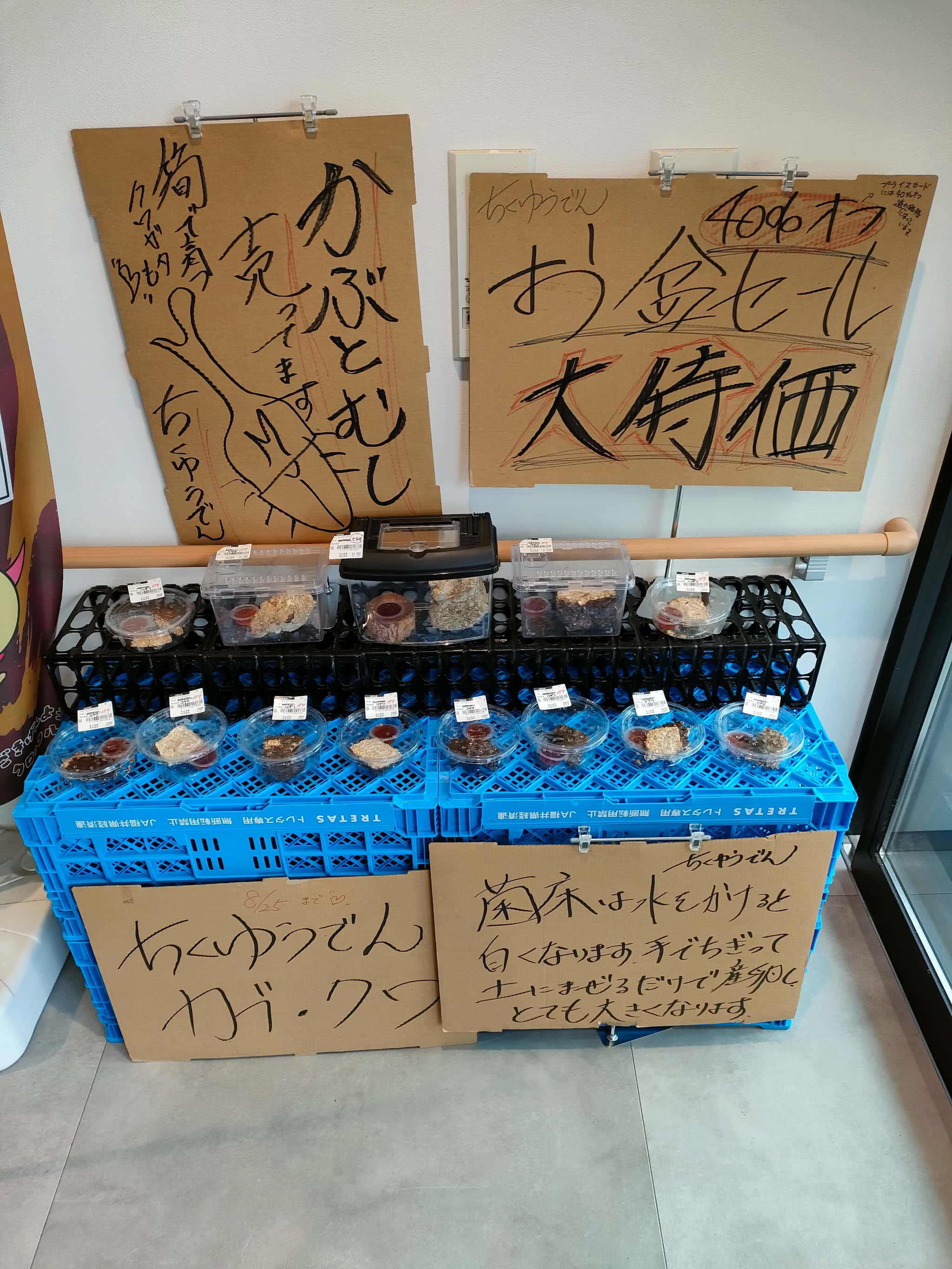
私が小さかったころは、カブトムシもクワガタも、九頭竜川の河原の木々が生い茂ってるところでいくらでも捕まえることができたものですが、もう、買わないとダメなんでしょうか?w
さて、今日のお題は「断熱材」です。先月の「夏場の熱対策は屋根が重要」に引き続き「暑さ」をテーマにしました。気温35度は日陰の直射日光の影響がないところでの空気温度でしかありませんので、実際に大きな影響を与えるのは「太陽の熱」なわけです。その熱量たるや凄まじいものです。
一般的なイメージとしては、この熱を「断熱材」が「跳ね返している」と思われがちです。でも実際には違います。物質にはすべからく「熱容量」という熱を蓄える能力があります。「断熱材」はその熱容量が極端に大きなものというわけです。ちなみに「熱容量が大きい」といえば、コンクリート、石、レンガなどがあります。言葉の表現にもありますように「熱しやすく冷めにくい」というのはまさにこのような物質のこといいます。例えば、石焼き芋の「石」は、強烈に熱されます。熱くなった石の上に芋を置くことで長時間、安定した熱が芋に伝わりあの美味しい焼き芋ができるわけです。逆に鉄などはすぐに熱くなります。そしてすぐに冷えます。「鉄は熱いうちに打て」は、鉄はすぐに冷えるのですぐに叩かないと加工できない、つまり迅速に行動しなければならないという表現なわけです。
「断熱材」は、鉄骨などの熱しやすく冷めやすい躯体構造に対して、「熱容量」を足し増すことで構造体全体の「熱容量」をアップさせるためのものです。できるだけ熱をためこんで、熱を他に逃げないようにすることができるわけですが、その能力にも限界があるわけです。外気温が30度くらいまでなら、高性能な断熱材で熱容量を超すようなことはないでしょう。その実は、夜中や朝方の気温が低いことで断熱材の熱が室内より低い外気に向かうことが多いので、あまり、室内に熱が戻ることがないのです。
ところが、35度を超す日が連日であれば、日中に降り注ぐ熱量はハンパないわけです。さらに夜中の気温も下がりませんし、朝方、太陽が昇ればすぐに30度です。そうなれば断熱材からあふれる熱は冷房をかけている室内側のほうに流れます。このため、エアコンは単に室内空気を冷やすだけではなく、壁や天井からあふれる熱をも冷やすような挙動をしますので、とめどなく動き続きますし、止めればすぐに室温は上昇するわけです。
こういう状況が、最近の情報番組などでも「熱がこもる」という表現で、エアコンを止めることができないという暑さ問題をとりあげています。マスコミもようやく、「何かが違う」と思い始めたって感じですw
こんな「断熱材」の話しをすると、断熱材は無能だと勘違いされるかもしれませんが、とんでもないです。夏は遮熱、冬は断熱、という熱に対する対応を変えることが必要なのです。断熱材は蓄熱材ですので、冬にはもってこいです。冬、ダウンジャケットなんかを着こむのと同じです。ですが、夏場にダウンジャケットなんか着ませんよね?それと同じことを建物でも考えないと、もはやあの強大な熱エネルギーに対応することはできないってわけです。
音源は出来次第コッソリおいときますw