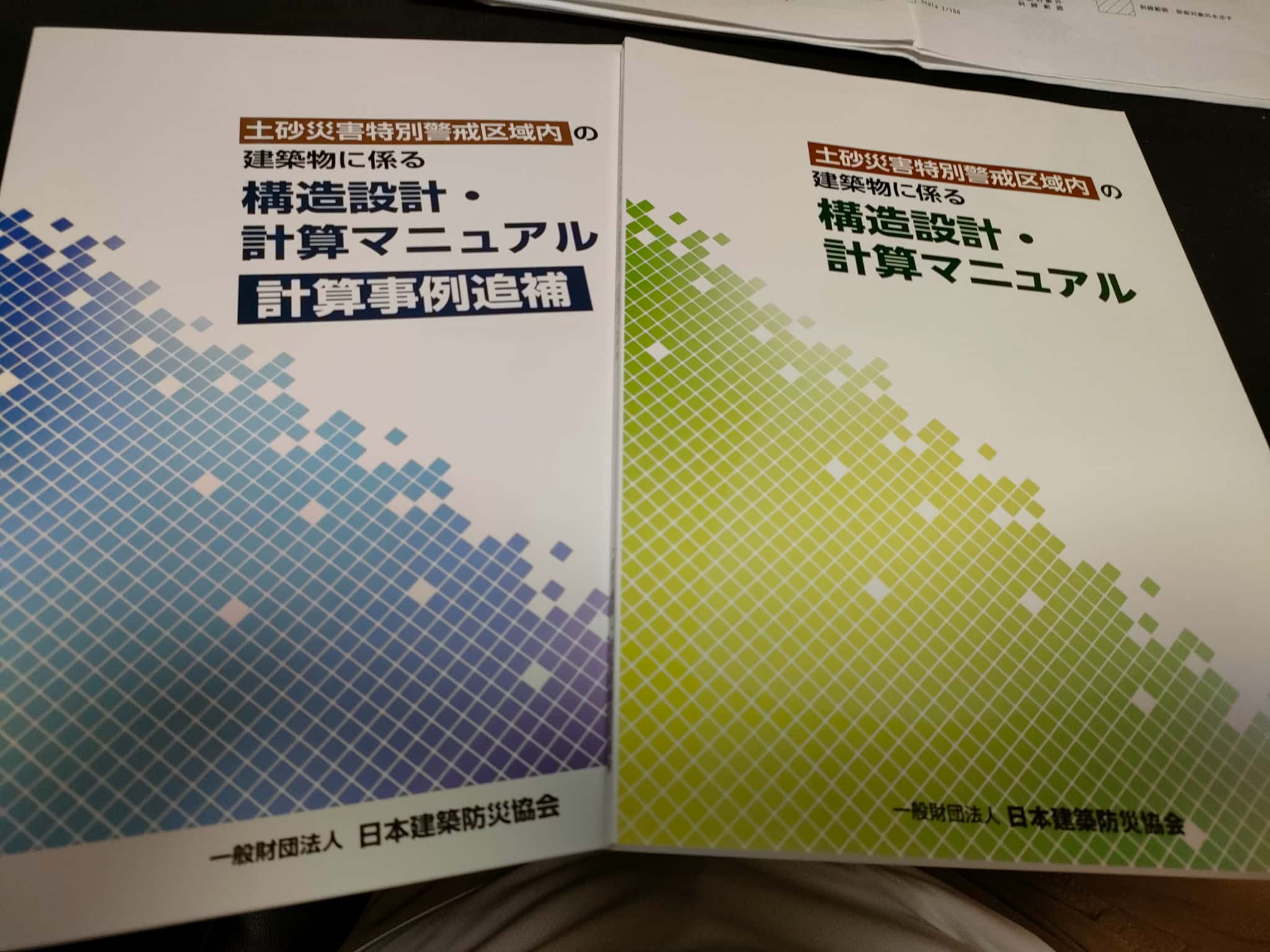9月24日は、ラジ+(TAS)にて第4水曜日にお送りしている弊社ラジオコーナー「福登建設の快適家づくり研究所」の放送でした。

今日のトレタスでは、「いちほまれ」の新米販売のキャンペーンがなされていて、アイドルの等身大パネルとともに宣伝してましたw

全国的に「いちほまれ」が有名になってくれればいいなぁと思います。
さて、今日のお題は「親子2世帯ローン」についてです。今でこそ住宅ローンの長期化ってのが当たり前になって、35年はおろか、40年、50年という長期ローンが商品化されています。ぶっちゃけ「住宅ローン」は金融機関にとっては、「とりっぱぐれのない鉄壁のリスク管理のローン商品」だと思ってます。土地、建物には1番抵当ですし、火災保険の加入はほぼ義務ですし、もちろん生命保険への加入も条件になってますので、債務者に何らかの不都合が発生しても、土地、建物を処分するだけでなく、保険などで返済を賄うこともできるわけです。
今から30年以上前の住宅ローンでは、金利も高く、償還期間もせいぜい20年程度で、結果として月々の返済額が借り入れ額を抑えたとしても大きくなる傾向がありました。単純な考え方として多額のローンを構築したとしても、返済期間(回数)が長く大きくなれば、月々の支払い額は減るわけで、家計に対する負担割合が減れば、それだけ借り入れ額を大きくすることができるわけです。
その手法として、「親」と「子」で住宅ローンを組むという「親子2世帯ローン」というものが結構、流行ったわけです。このローンには3つの形態があって、
①親子リレーローン
②親子ペアローン
③連帯債務による親子ローン
となります。
①については、契約上、親と子が契約者となりますが、最初は親が返済し、親になんらかの事情が発生した場合に、そのローンをそのまま子が引き継ぐというものです。もちろん、親が完済すれば子に返済義務がないわけですが、逆にローン締結後すぐに親に事情ができて返済できないとなれば、子にリレーされるというわけです。
②は、親と子それぞれがローン契約することで、親は親の分、子は子の分として2つの住宅ローンを履行することになります。各々が返済することで、返済金は減らせますが、それは見かけの額でしかなく、保険なども二人分かける必要がありますし、もちろん親の分を完済しても子がまだ継続中であれば、子のローンは残っている状態になります。
③は、これがもっとも危険だと感じています。これは、主債務者として「親」がなりますが、同時に「子」も債務者としての立場につくというものです。主債務者としての「親」が返済不能となれば、即時、「子」に返済義務が発生します。この「即時」という部分をあまり理解していない方が多いのです。例えば、親のローン引き落とし口座が残高不足であった場合、ローンの返済が滞ることがあります。その場合、「即時」ですので、落ちないことが確定した段階で子が変わって返済する必要が出てきます。ですが、現実問題として、残高不足で落ちなかったことを知ることは、少なくとも「子」がそれを知るタイミングは遅くなります。そして支払い期限の月をまたぎますと「金融事故」を起こしたということで、親も子も信用情報にNGが付くことになります。
実はこのパターンは特段不思議なことではないのです。親が退職後、年金だけが収入源だったとしますと、年金は2か月に一度の入金になります。ですが、返済は毎月ですので、タイミング的に、退職翌月にまだ年金受取りなってない場合など、口座に残高がなくなることが予測されますが、2か月後には入金がありますので、前月に返済が滞っても次月に2か月分引き落とされることで、「ちゃんと支払われている」という勘違いが発生します。これを1年繰り返しますと、年に6回の金融事故を起こしたことになりますので、ほぼ信用がない状況になります。そして、それが「親」だけではなく、即時返済義務が発生する「子」にも影響するというわけです。なぜなら連帯債務者ですから、親が払えないなら子が払わないとダメな契約になってるからです。すると、子も全く感知していないところで自分の信用情報に傷がつくことになります。金利が低く設定されるような他のローンはほぼ通りません。
そして問題なのは、子が「親子2世帯ローン」で債務者になっていることを知らない、ほとんど意識していないことにあります。30年以上前に親が住宅を新築しようとして借り入れるときに、金融機関から「親子2世帯ローン」すすめられることが多かったわけですが、その理由は、親単独での借り入れではあまり借りれない、期間も長くできないということから、安易に親子2世帯ローンをすすめることがテッパンな営業だったわけです。
親は子に迷惑をかけるつもりはありませんので、子の負担にならないように自分が返済していくと意識しますが、結果として寄る年波に勝てず、定年を迎えても借り入れが残るような状況があるわけです。子にしても、親から「ちょっとここにサインしろ」とか言われて、なんか家を建てるとかで署名がいるんかな?くらいにしか考えず、親の言うことだしでサインするわけです。その際に、しっかりと親子2世帯ローンの契約形態を説明し、理解させるようなことは「ない」わけです。これが不幸の始まりというわけです。
①から③どのパターンでも、子はすでに住宅ローンを抱えているわけですので、自分の生活や人生設計で「別居」が必要になるとか、新しい家族ができ所帯を独立させたいと考えても、住宅ローンを組むことは不可能になります。そして、その時にはじめて、自分が置かれている立場を理解する人が圧倒的に多いわけです。親は、「自分が返済しているから子供には関係ない!」と言いがちなんですが、それは子供と一緒に返済することを担保としているわけで、親の信用だけではないことを理解していません。借りるときに「借りれればいい」ということだけで、目先の利益に飛びついた結果なわけですが、それは子のことを考えた結果ではないのです。また、子の世帯ができたとして、その世帯と親の世帯の関係性が劣悪になる状況も想定できます。親子2世帯ローンには、そうした状況など全く関係ないのですから、本来はそうならないような工夫や努力も必要なのです。
いずれにしても、過去に自分の家を住宅ローンを利用して建築したということを覚えている子の世帯は、今どうなってるか?は確認すべきなのです。
音源はコッソリおいておきますw