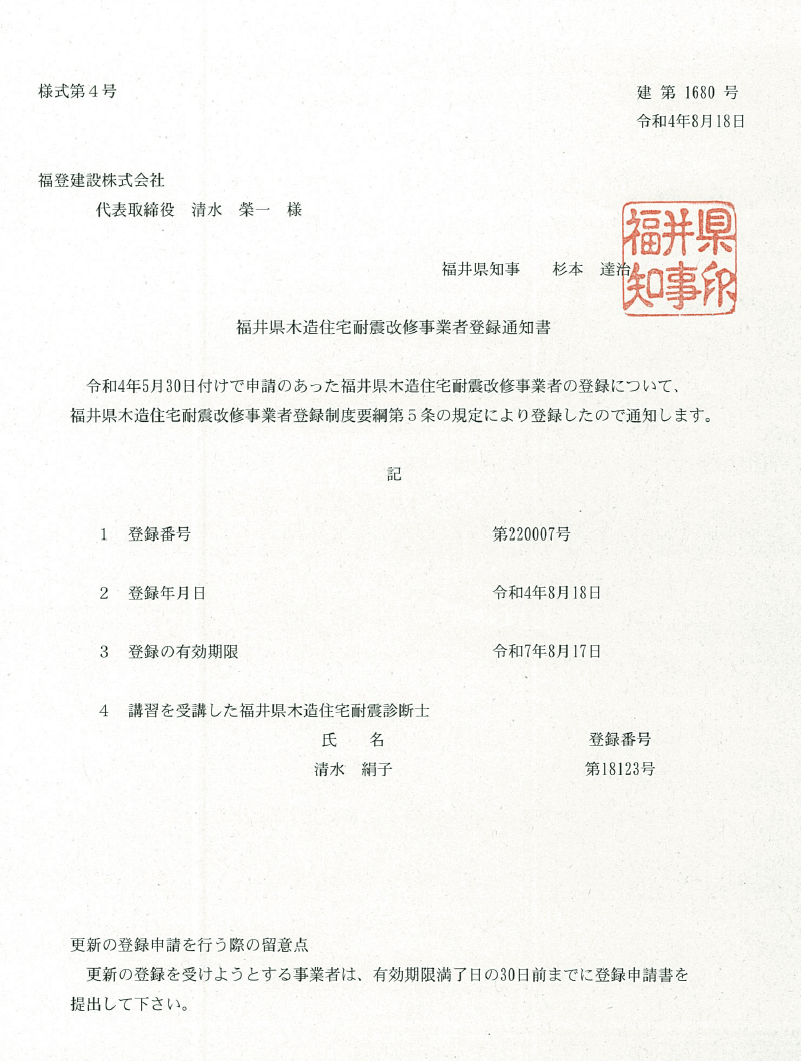建物の防音性能って、近隣トラブルにつながるような話しなんですが、実際、建物の設計をする際に意識するってことはあまりないのが現状かもしれません。耐震性や省エネ性能を満足することについては注視しても、「防音性能」というレベルでは、音楽教室を併設したり、自宅でピアノなどを練習したり趣味になさっている場合や、ホームシアターなどの音響と映像を趣味とされる場合など、特殊な場合への性能対応としか考えないと思います。
確かに、現在の建築様式で、省エネ性能を上げるために壁に仕込む断熱材やペアガラスや樹脂サッシなどを利用することで、古い住宅様式よりも防音性能が上がっている部分もなくはないです。一般的には「壁の密度」が高ければ高いほど「防音性能(遮音性能)」は高くなります。これを「質量則」といっています。
在来木造の壁は、柱に壁の下地になるボードを張って、柱の部分は中空になるのですが、この部分に断熱材などが入り、かつ、「石膏ボード」などが張られれば、それなりに壁の質量は上がります。質量則に従えば、鉄筋コンクリート造の壁は相当な質量(密度)ですので、防音性能は高いってわけです。ところが、実際にはそう単純な話しではなく、音の周波数帯によってはなかなかカットできないケースもあります。
実は一般的には「高い音の周波数」に対する防音対策は楽です。ちょっと壁をごっつくすれば、まず、聞こえなくなります。話し声レベルなら十分だと思います。でも、「低い音の周波数」に対する防音対策は結構難儀することが多いのです。例えば、2階で床に鉛筆を落としたときに、「カン!」っていう音が響きますが、「カ」は聞こえなくできますが、「ン」がカットできないっていうイメージです。
生活音を気にならないようにするというレベルでも、「なんか響く」っていうことが気になる場合、「低い音の周波数」さらに言えば、「聞こえないレベル」の低周波が「振動」として感じることが多いわけです。
これらの防音対策には、使用する部材の「遮音レベル」が問題になります。防音性能を担保する部材には、「D値、L値、T値」といった、「遮音性能」のレベル表示がなされています。それらの値によって、音がどの程度、透過してしまうか?というものを表します。でも、実際、これらの性能が高いから満足するか?というとそうでもないところが、防音対策を設計で考える上で非常に重要になるわけです。
というわけで、SNSでこんな告知がなされてました。
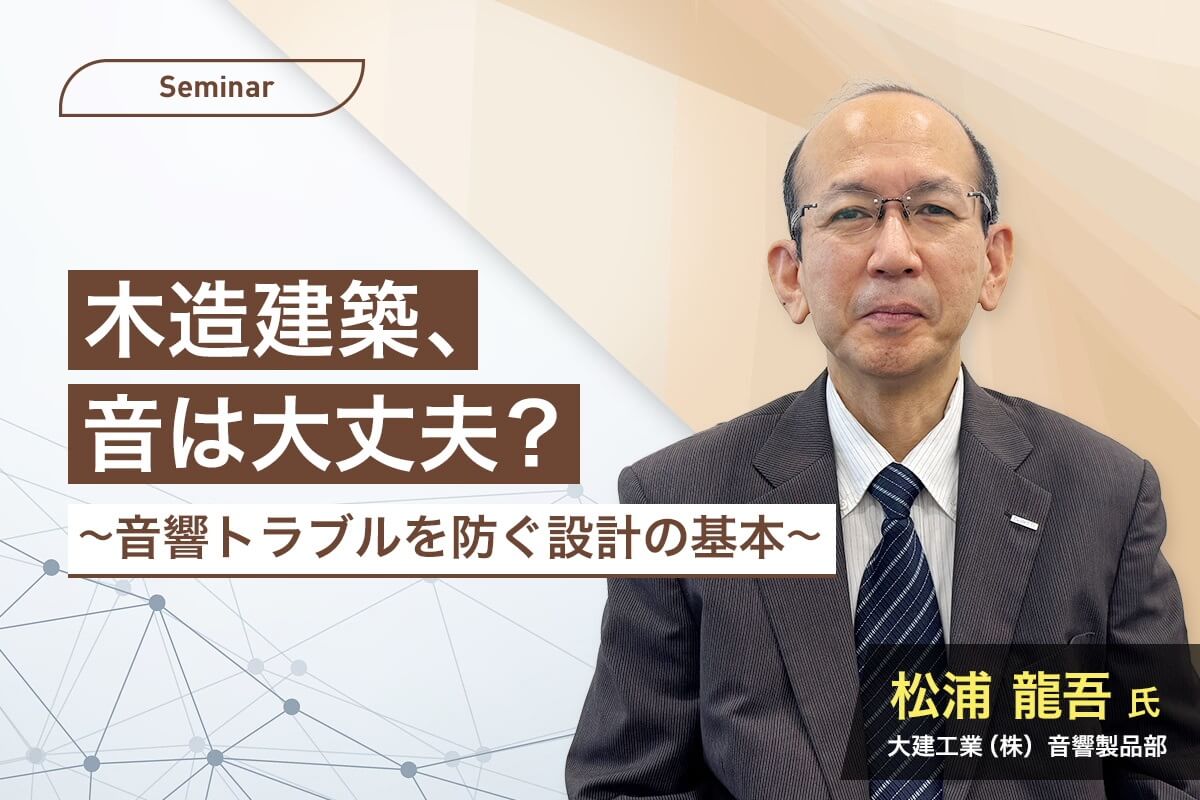
大建工業さんの主催セミナーです。大建工業さんは、昔から、防音・音響に関する建材の開発販売をされていて、結構、参考にさせてもらうことが多かったんですが、オンラインでセミナーを行うということで、早速、申し込みました。
耐震や省エネが当たり前になる中、防音とか音響の部分がおいてきぼりにならないように勉強したいと思います。