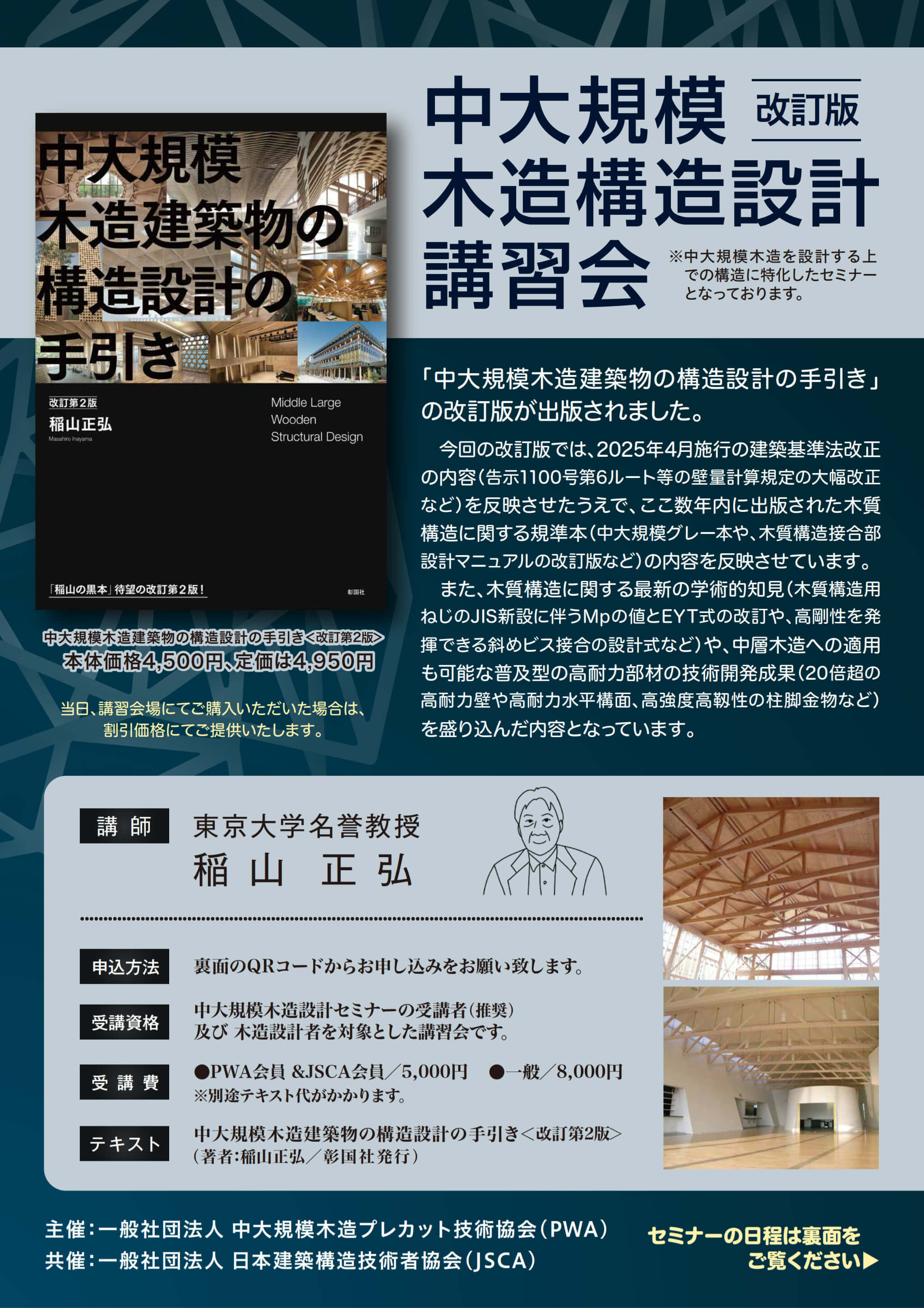アルアルシリーズですw 今日のネタは「ええええ!」というような、悪い状況の話しじゃありませんw
耐震診断はご依頼される建物が確実に昭和56年6月以前に建築された古い住宅です。住宅とはいえ、たいへん古い「古民家」と言われるような建物もあれば、建売として建築された戸建てもあります。ですが、たまに、まるで、「建築の教科書」、それも「設え」や「デザイン」的な教科書に出てくるような仕上げや間取りになっていることがあります。
古い住宅とはいえ、建築時点の「こだわり」が如実に現れていて、ちょっとした建具廻りの納めなども、非常に手が込んでいるような場合、築50年経っていても、単に仕上げなどが古いというだけで、見栄えは全然ちがいます。なんといいますか、洗練されているという感じです。
現在では既製品建材の発展で、建材を採用するだけで豪華であったり、重厚感ある仕上げにすることは可能です。でも、今から50年以上前の建物では、「新建材」と名の付く建材はやはりどこか「チープ」なイメージがあったのは確かです。仕上げは「左官」が当たり前だった時代から、乾式工法としての「新建材」に移っていった時代では、建築コストもかなり差が出た時期でもあります。
お伺いした住宅は、昭和40年代に建築された、280㎡を超す大きな住宅です。「お屋敷」と言っても過言ではありません。都会の280㎡と言えば、階数がある、要するに上に伸びる建物構成ですが、福井の280㎡は、大きな1階間取りに、2階が少し載るといったイメージが強いです。ちょっと画像をお見せすると、


これ、トイレなんですが、左手に洋式便器、右手に小便器が配置されています。洋式便器側はおそらく、トイレ改造されている状況で、元は和式のトイレだったと推測できます。一般的にこのような場合、洋式便器と小便器の間のスペースには手洗いや洗面が取り付くと思いますが、そんな無粋なものじゃなく「蹲(つくばい)」なんです!

換気も重視されてて、木板をスリット状に開け閉めできる建具がつけられています。画像よく見ていただくと、蹲の前に手摺がありますが、少々アールをつけて格子状にしています。洋式便器の方ですが、床部分にちょっとした明り取りを配置してます。

これらの設えは、色や材質で雰囲気を作っているのではなく、建具や指物などで雰囲気を作っているわけですが、こんなものが料亭や高級旅館では見れるかもしれませんが、「一般住宅」でなされているというのは正直、「稀」だと思います。そして極めつけは、小便器側です。

よーくご覧ください。右側の壁ですが、カメラの高角のせいじゃなく、壁が「斜め」になっているんです。奥にいくと壁が内側に入っているってわけです。普通、トイレなんですから、真っ直ぐ壁を作ってもかまわんと思うのですが、なんとなく、こだわりを感じます。
耐震診断で様々な住宅を訪問しますが、このような古い建物でも、こだわりを持って建築されている建物をみますと、一息、関心して見惚れてしまいます。お話しをお聞きすると、亡くなられたお母様が、相当なこだわりで建てられた「ドリームハウス」だったようです。
構造的に見ても、ほとんど柱の傾斜はありませんし、変な床鳴りがする部分もありません。昭和40年代では基礎は外周部のみというところが多いなか、鉄筋コンクリート造の基礎が施され、柱を石で受けるようなこともありませんでした。
耐震診断の結果として、どうしてもNGにはなりますが、単なる数値では判断できない「設計の丁寧さ」というのは建物の維持という側面では非常に重要であるということを、まさに時間経過が物語っていると思います。
ご要望としては、できるだけ見た目を変えない耐震補強計画をです。当然だと思います。診断士の中には、やみくもに耐力壁を増強されたりしますが、結果として建物のデザイン性を含めた「こだわり」を潰してしまいます。できるだけ改修箇所を絞ったり、改修方法を工夫することで、今の建物の雰囲気を維持するということも耐震補強プランには必要な考慮の一つだと考えています。