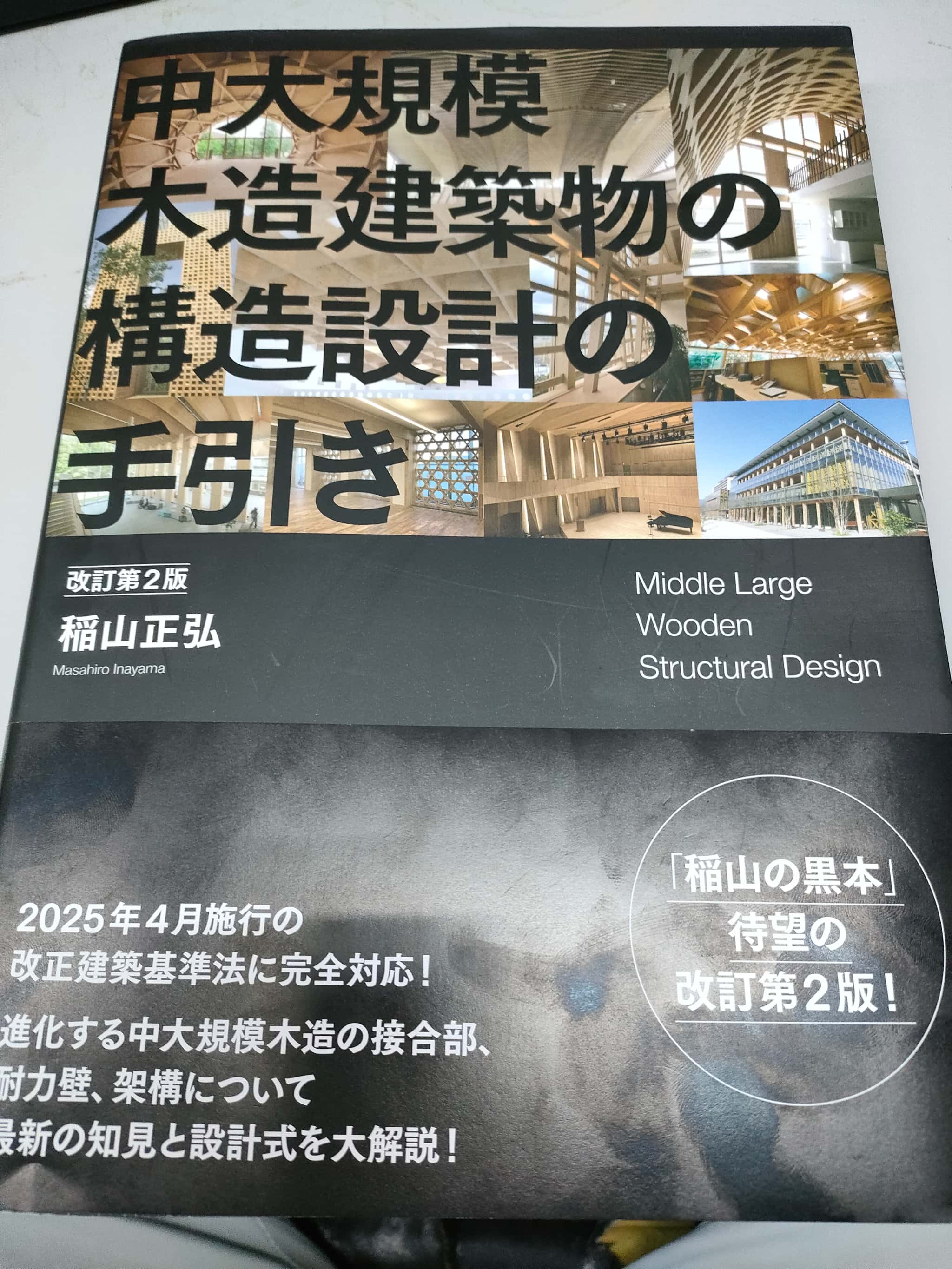アルアルシリーズですw 耐震改修で壁を壊すのはまぁ当たり前として、前回#14ではびっくり仰天の「設備」だったのですが、今回のご紹介は「土台の朽腐」です。まずは解体前の様子をご覧くださいませ。


勝手口の部分が日常的な荷物置き場になっていたわけですが、耐震化という部分では、生活する部屋ではありませんから、改修でしばらく使えなかったとしても差し支えない場所で、補強プランを検討する上ではもってこい!の場所であることは間違いありません。さらに仕上げもケイカル板か石膏ボード仕上げで十分ですので、コストも低く抑えることができますし、天井を壊したところで畳1枚程度の復旧ですから、非常に工事がやりやすいところなわけです。画像に写っている両側の壁面を強固な耐力壁とする計画です。
でも、いざ、解体となったときに、中の荷物を移動したところ・・・・

土間コンクリートに、いやなシミがw まぁ、灯油なんかもありましたので、それが原因かなーと思いましたが、そもそも論、勝手口サッシの下の部分には隙間がありますし、ある意味、ここの室温は冬場ではほぼ外気温と同等になると思いますので、隣接する部屋で暖房がきいていますと「結露」の心配は出てくるわけです。この「いやなシミ」が結露によるものではない、灯油であってくれ!と願いながら壁を壊したところ・・・・


喰われておりました・・・・
状況をくまなく調べると、柱は問題なく、土台がやられている状況です。防腐防蟻材の塗布は確認されましたが、まぁ、そんなものが一生問題なく効果が持続するわけではありません。ちなみ、防蟻処理薬剤散布は、もって5年です。厚生労働書認可の薬剤は、その成分や強さには限界がありますので、持続期間はこの程度です。したがって10年もちます!とか20年もちます!は、認可されていない薬品の使用の可能性もありますので、人体への影響が懸念されます。薬剤は「揮発」がありますので。
ですから、防腐防蟻処理は、薬をまけばいいというわけではなく、如何にシロアリの温床になりやすい環境を作らないか?なわけです。これには2つの方法があります。
①耐久性の高い木材を使う。
②濡れないような環境をつくるか、濡れてもいいけど、すぐに乾く環境であること。
シロアリは、柔らかい木を食べます。その餌になる木があれば、コンクリートが邪魔をしていればそれを食い破ってでも餌に到達しようとします。家の中の木材だけではありません。家の外にストックしている木材も食べやすければ食べに来ます。よく田舎などで住宅の犬走にどこかで拾ってきた木材を積み上げてとってあるところが多いですが、あれ、シロアリを呼んでるようなもんですので、少なくとも建物からは遠ざけてほしいのです。
さて、建物の中なのになんで濡れるの?って思うかもしれません。この原因が「結露」であることが多いです。また、シロアリによる被害だけでなく、濡れることにより腐朽菌が繁殖しどんどん木材を腐らせることにもなります。これが多いのがタイル張りのお風呂の土台だったりします。
耐震改修の際には、こうした「土台の朽腐」に出くわすことは結構な頻度でありますが、もちろん、朽腐した土台の修復をしなければ、その場所での耐力壁の強化などできません。一仕事増えることになります。