建物を設計するときに、様々な規制を受けるわけですが、一般的には「建築基準法・施行令・規則」という部分を踏まえれば問題はありません。でも、実は、国が定めた「建築基準法」は準拠しなければならない法としては一番低レベルに位置しており、イメージとしては「とりま、守っとけよ?」なレベルでしかありません。それよりも優先される法が、各都道府県や各市町が制定している「条例」や「細則」、「規則」といったものです。イメージとしては、
建築基準法 < 都道府県基準 < 各市町基準 < (地区の協定など)
という感じです。言い換えると、建築基準法では特段規制をしていない内容でも、都道府県基準や各市町基準などが細かいルールを決めている場合があって、確認申請の審査では当然、建築場所の細かいルール上の審査もされるということです。
これらはいわゆる「ローカルルール」であり、各地の気候風土や風習などに対して対応するための最低限のルールなわけですが、福井県においては結構、厳しいローカルルールがあったりします。それが、
「福井県建築基準条例」
なのです。これで痛い目を見た建築士はたくさんいて、「悪魔の条例」という表現がバッチリあってくるものもありますwww
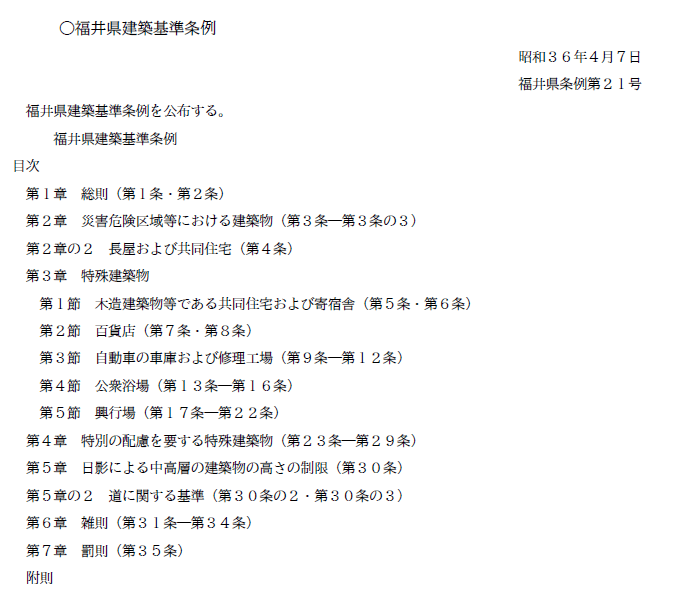
これが「福井県建築基準条例」の目次になりますが、多くの自治体で決められていることもあるので、すべてが「悪魔の条例」とはいえませんw 悪魔な内容をご紹介しますと、
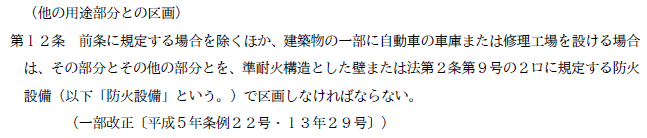
もしかすると、他の都道府県でも規定されているかもしれませんが、福井県では車庫に関する規制が厳しく、一般的な建築基準法での運用では告示によって「面積緩和」で30㎡未満の車庫は「車庫として扱わない」というのがあるんですが、福井県では、
「車止めるなら車庫な?」
ってことで緩和は認めません。それがこの「県条例第12条」で、この条文に対する面積緩和について記載がないため、何㎡であってもこの第12条が適用されますw 車庫自体の計画はさほどハードルの高いものではありませんが、この第12条に記載されている「区画」が問題で、例えば、玄関前に車庫を作って雨に濡れないで入ろうとすると、玄関ドアは「防火設備」として規制を受けますし、車庫に面する壁は「準耐火構造」とした壁でつくらなければなりません。
建築基準法での規定でも異種用途区画という規定があり、車庫についても規制を受けますが、基準法では面積で規制を受ける受けないがあるにも関わらず、県条例ではその条文がないため、第12条を要求されるというわけですw 悪魔ですwww しかも、これは建物の用途に限らないので、住宅でちょっとビルトインガレージにしたいとなれば、車庫から室内に入る建具は「防火設備」とし、住宅部分に接している壁は「準耐火構造」にしろって感じになりますので、コストが増大します。マジで、防火設備の建具はハンパない金額ですw
次に紹介するのは、同じ車庫なんですが「前面空地」というものです。
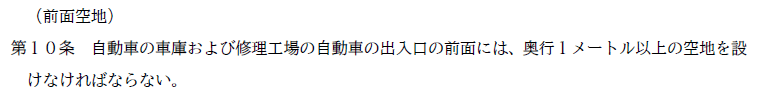
条文が前後しましたが、こちらももちろん「車庫の面積緩和」はありません。「車庫」となった瞬間に、前面空地を求められます。車庫にシャッターをつけるなら、そのシャッターのスラット面から1m空地になってることを求められます。まぁ、これは車庫の出入りの際の目視確認のためのスペースでもあり、あと、除雪の際に雪を押すことでシャッターのスラットを雪で押して壊してしまうことを防ぐことにもつながっていますので、あながち「悪魔」とは言えませんwww でも、敷地の状況では1m下がることで満足いく奥行が取れない車庫になったりもしますので、結果としてシャッターを閉められず車のノーズが出ちゃってるってことにもなります。
次は施設関係の規制ですが、ホントマジでイラっとくるやつですwww
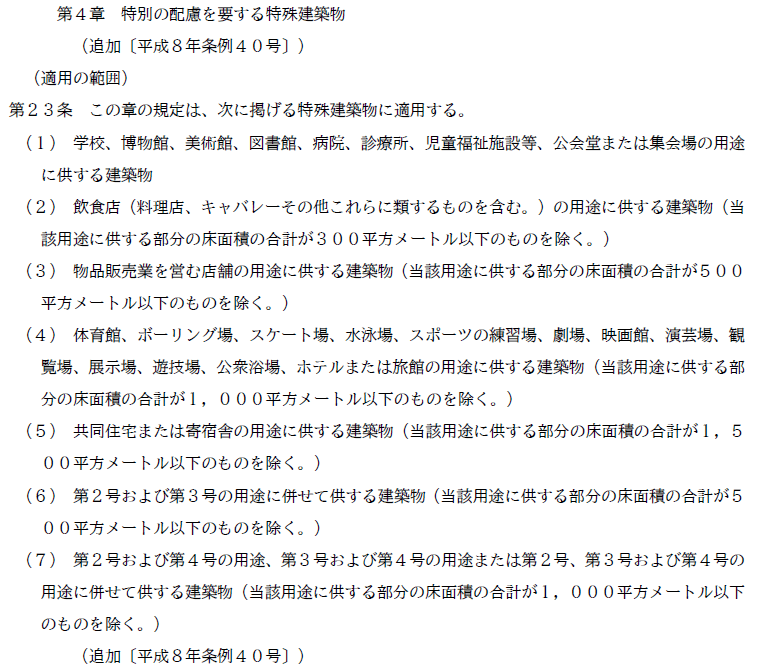
「特別の配慮を要する特殊建築物」というものを規定しています。(1)から(7)まで読んでも、そう滅多に設計するようなことがないと思われるかもしれませんが、(1)に「児童福祉施設等」ってありますよね?これ、「児童福祉法」とか「医療法」とか「身体障害者福祉法」などの福祉関連の法律で規定されているもので、結構幅広くあったりします。
例えば、「保育所」は、この「児童福祉施設等」になります。でも、幼稚園は学校なので違うw あと、放課後見守り保育とか、児童を預かってお世話をするような施設も「児童福祉施設等」になります。店舗とかも特殊建築物ではありますが、規模が小さいものはほとんどこの条例には引っかからないのと、事務所とかテナントも引っかからないので、中には、児童福祉施設関係なのに事務所として申請して、あとからどえらいことになるなんて事例もあるようです。
で、どんな規制を受けるかというと、まず、「出入り口」です。
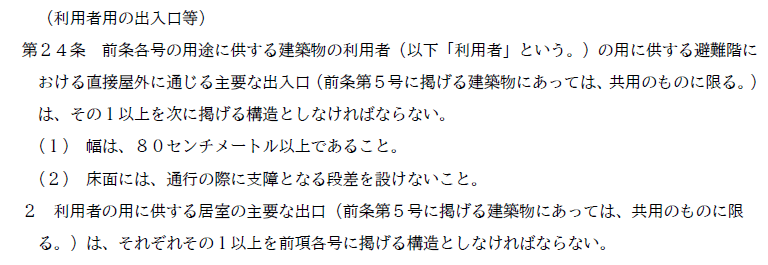
ドア開口は80cm以上っていう規定があるので、一般的な住宅のドアを使うってわけにはいきませんw あれ、大きくても78cm程度なんで住宅部材で建築するなら「両開き」の選択か、特注でデカいドアにするしかありません。
さらに、避難路についての規定があります。要するに、第23条で規制する建物を決めて、24条では出入り口を規定して、その後に通路の規定が続きます。
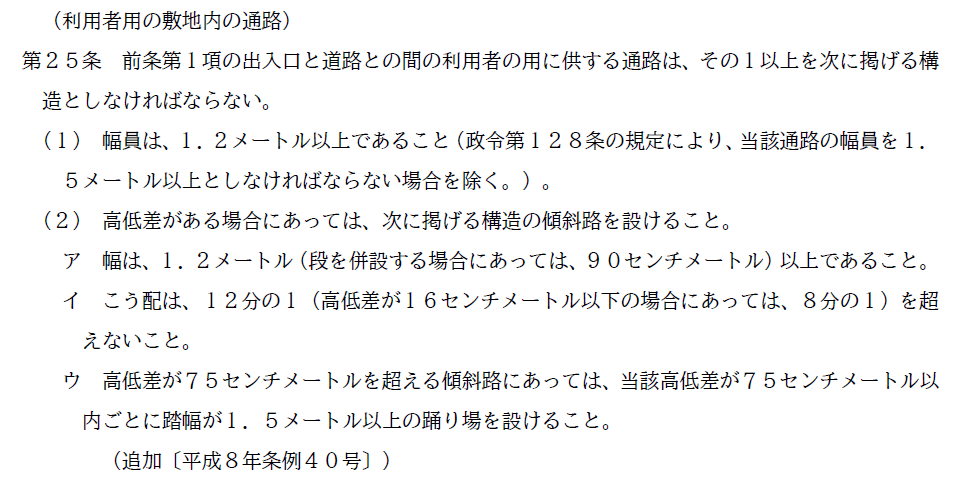
「敷地内通路」というのは「建築基準法」にも規定があるんですが、県条例では通路の高低差を認めていませんwww 「傾斜路」つまり、「スロープ」を設置するように求めています。幅は1.2m以上で、勾配は1/12ですw 高低差が16cm以下の場合には少々きつくてもよいので1/8となっています。
これを具体的にいいますと、玄関と玄関ホールの床の高さが違う場合には、その段差の高さに応じてスロープでアクセスできるようしろ!というわけです。ちょっと具体的に事例を示しますと、



玄関の床土間がスロープになって、そのまま床の高さと同じにした例です。木造ですので、基礎があって土台があって床があるわけで、どうしても湿気なんかの関係もあってできるだけ土台を土間コンクリートで埋め込んでしまうということは避けたいというのもあり、玄関の土間をスロープ化しています。もちろん、玄関ドアを一般床の高さまで上げることでも、対策ができれば問題ありません。
そして、さらに室内側の「通路」にも条例規定がありますw
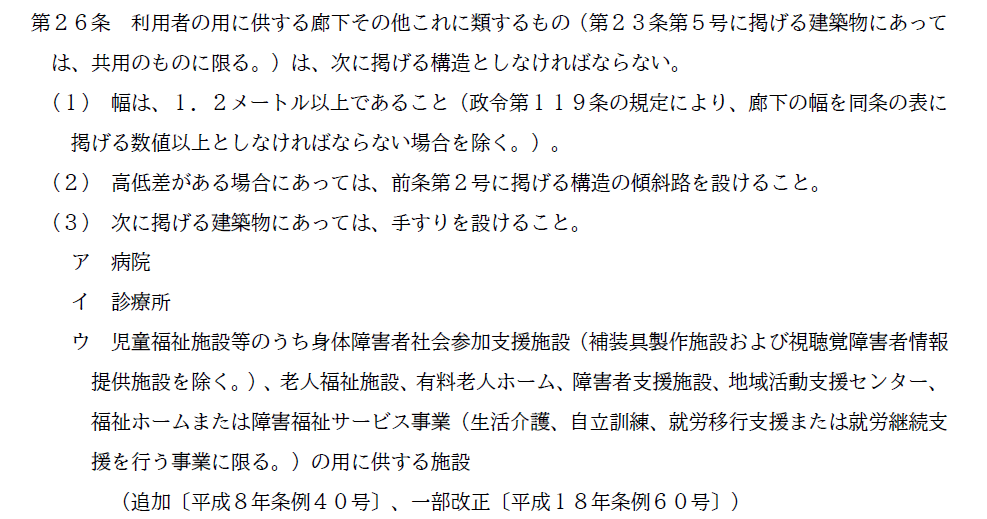
これは、廊下幅の規定ですが、これも「建築基準法」に規定がありますが、問題にしたいのはこの第26条の(2)ですw 段差を認めてませんw そして、そのスロープ仕様は前条と同じですwww
大きな床面積の建築であれば、比較的、斜路を計画するための長さを確保することはできますが、住宅レベルの面積で計画するような場合には、配置状況や間取りの構成ではかなり難儀します。
そして、一番やばいのは、基準法レベルでは特段指定がなかったり、緩和規定などで規制を受けない場合にでも、この「県条例」での規定が「後だし」のように迫ってくるという実態です。もちろん、有資格者ですので、その点の条例確認は当たり前ではありますが、その解釈が間違っていたりすることもあるので、かなり厳しい修正を余儀なくされることになります。
まぁ、「慣れ」ればすむことですがwww



